| 段々長く | 絵回文 | 気紛回文 | 漫画回文 | 野球迷鑑パ | たいこめセ |
| 段々長く | 絵回文 | 気紛回文 | 漫画回文 | 野球迷鑑パ | たいこめセ |
| 哀憐峠クリック順1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 |
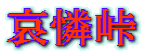 (最終話)
(最終話)

![]()
| 「無事であればよいがのう」 「御意、日の暮までに探し出せればよいのですが」 捜索隊を送りだした龍興と忠頼は元の座に腰を据え落着かない様子である。 「案じても詮無いこと、吉報を待つしかあるまい」 「頼の不始末からあらぬご心労を・・・」 「又その事か。よいと申したではないか、義康殿の娘御の危機を知っては黙っても居れまい」 「その亡き殿(義康)は此の手で殺めたのです」 「後悔しておるのか」 「いえ、武士としての条理は通したつもりはありますが、裏から見れば身勝手としか見えぬ所業だったかと」 「婿選びと称し片腕と頼む家臣に真剣勝負をさせるとは言語道断、決して赦される事ではない。忠頼殿に罪は ない、お気に召さるな」 「されど其の為に姫までが失踪なされました」 「それとて、ご貴殿が追い出した訳ではあるまい。全ては運命なのだ」 「其の運命を悪しき方向へ向けた責はこの頼にあります」 「そう己ばかりを責めるでない、余はご貴殿に会って人の心を知った。禄高も充分でなかった貴殿が、弾みで 城主になられたようなもの、普通なら舞い上がって傲慢になり、他人の不幸など目につかぬものだがご貴殿 は勝手に出ていった小夜にこれ程心を砕いておられる。これは余にも真似の出来ぬ事だ」 「姫のご無事を見届けたらこの身は龍興様の手にかかり果てようと覚悟しておりました」 「何を言うか!余がそれ程の判らず屋に見えるか!」 「決してその様な意味では・・・」 「望みとあらば成敗してくれる!そこへ直れ!」 「ははっ!」 「はっはっは、冗談が過ぎたな。許せよ」 「お斬りにならぬのですか」 「余の心がまだ判らぬか、余は比羅保許の城主として対等の立場でもの申しておるのだ、小夜の生死がどうで あろうと天意に任すのだ。城主として比羅保許の安泰を守って行く事こそ使命であろう。困った事があれば 余が何時でも力を貸そう、もう義康殿の事は忘れろ」 「有り難きお言葉、このご恩は生涯忘れません」 「泣いておるのか」 「いえ、目に埃が入ったようで・・・」 「困った塵よのう、はっ、はっ、は・・」 忠頼は泣いていた。成敗されなかった事で安堵しての事では無い。龍興の心の深さに感じ入っての泪である。 日は西に傾き、薄闇が城の麓から忍び寄ってくる。捜索隊からはまだ何の連絡も無い。 二の酉を告げる鐘の音がおどろに響いた。いつもなら閉ざされる城門は開かれたまま、明々とした篝火に、 人影が揺らぐ。吉報を待つ幾つもの顔が眼下にのたうつ街道を凝視したまま、微動だにしない。捜索隊を 鶴首する焦りは門番にまで波及していた。 その街道の薄闇に波のように白い旗が流れ、次第にその数を増してゆく。 「捜索隊が戻られたように御座ります」 正面の床几に陣取った龍興、忠頼の元へ見張りの者が注進に及んだ。 「おお!待ち兼ねたぞ、篝火を増やせ!酒肴の用意は抜かりないか」 泰然と構えていた龍興が待ち人を迎えるような燥ぎようである。 ――吉か・・凶か・・・。 忠頼は心で問答しながら動こうとしない。お甲が遠くから様子を窺っている。 やがて蹄の音も荒々しく陸続として騎馬隊が門を潜り到着した。 「ただ今戻りました」 厨田敏忠が龍興の前に跪く。他の捜索隊もそれに倣った。 「敏忠殿か、ご苦労であった、して小夜は如何致した」 落着いた声ではあるが、小夜の安否を真っ先に問うた事にこそ、心の揺らぎがあった。 「実に残念ながら・・・・」 あとは絶句し、敏忠は傍らの荷馬車の覆いを剥ぐよう促す。平九郎がその覆いを剥いだ。 「姫様は茂市と共にお果てでした」 敏忠の血を吐くような声が嗚咽となる。 「姫様ぁ!」 お甲が走り寄ろうとして止められ半狂乱になり泣き叫んでいる。 「二人の発見場所は異なるのか」 「いえ、二人とも狭い洞の中で折り重なるようにお果てでした」 「何故小夜だけがずぶ濡れなのだ」 「思いまするに、あの日は落雷を伴う大雨が降りました。逃げ遅れた姫様がその雨に打たれたものと 思われます」 「その様な筈はありません」 掃部が解せぬとばかりしゃしゃり出た。 「控えぬか!掃部」 忠頼が慌てて制す。 「構わぬ、申すがよい」 龍興が掃部を呼んだ。 「はい、卒爾ながら、ここに眠る茂市は忠義一途な若者、姫様にお仕えする事を至上の歓びとしていた男で 御座います。その茂市が姫様を危険に晒した侭先に逃げるなど考えられませぬ」 「成程、して小夜のこの姿をどう見るのじゃ」 「其処までは爺にも判りませぬが、誓って茂市はその様な卑怯者ではありません」 「控えよ、掃部!」 堪らず忠頼が再び𠮟咤する。龍興への無礼と見たからである。 「よい、よい、手下思いの家老の言い分にも一理ある。見れば茂市とやらは自害して果てたと見ゆるが、小夜 には傷一つ見当たらぬ。妙だとは思わぬか」 「卒爾ながら平九郎が申し上げます」 「何じゃ、申して見よ」 「さすれば発見した時の様子から推して考えまするに、姫を守り通せぬと観念した茂市が自刃、其の後姫様が お一人で湯沢へ向おうとしたが驟雨に打たれ断念して洞へ引き返したのち、命尽きたのではないかと存じます」 「そうか、それで小夜だけがずぶ濡れであった事も合点がいく。亡き者の死をこれ以上詮索しても仏の供養には ならぬ。手厚く葬ってやるがいい」 龍興は篝火を背にし去った。其の背は気丈に振舞っているようで寂しげである。実際、両の眼には泪を溜めて いたのだが、城主として家臣たちに悟られてはならぬ泪であった。 峠の崖から身を投じた小夜が何故洞の中で茂市と共に発見されたのかは謎なのだが、事の次第を知らぬ比羅保許城では 謎を謎とも思わぬ龍興であり、忠頼でだった。 |
| 小夜と茂市の弔いから一年が過ぎた。塩根坂峠は初夏の陽射しの中に微風を纏い、初蝉が鳴き小鳥の囀りに何事も無かった かの如く長閑である。近頃は茂市が身を挺して薙ぎ払った跡や、騎馬隊が登った坂が道となり野削(のそぎ)や湯女沢への 近道として峠越えをする者も次第に増えつつあった。 杣(そま)の萬造が湯女沢へ妹を訪ねこの峠を越えようとしていた。 「やれやれ、馬の登った坂と言うが、酷ぇ道じゃねぇか、小夜姫様はどうやってこの山を越えたんだ」 愚痴と驚きを半々に呟きながら山頂の切株に腰をおろし汗を拭き煙草を噴いた。その腰には握り飯が括りつけてある。 「な??何だ?!!」 腰の包みを何者かに引っ張られ萬造は切株から転げそうになった。見れば狒狒(ひひ)かと紛うばかりに白髪を肩まで 垂らし髭ぼうぼうに痩せた老人である。 「このおいぼれめ!太ぇ野郎だ!」 怒った萬造は首根っこを押さえつけ左右に揺さぶった。老人は ”ひぃひぃ” 言いながら逃げようと踠くが空腹の為か 力が入らぬらしい。萬造は向きになった自分が馬鹿らしくなり、 「おととい来やがれ!」 足蹴にすると老人は枯木のような足を天に向け引っ繰り返った。股間から萎びた泥芋のような魔羅が覗く。 「太ぇどころかまるでカマキリじゃねぇか」 萬造に嗤われ老人はバツが悪そうに立ち上がった。 「おい爺さん、腹が減ってるんなら何故 ”一つお恵み下さい” と言わぬ、素直に出れば一つぐらい恵んでやてもいいぜ」 萬造は腰の包みを解きかけた。 「拙者とて元を糺せば沖蟹蛭蔵(おきがにひるぞう)と言うれっきとした武士。痩せても枯れても乞食の真似は出来ぬわ」 「蟹だか蛭だか知らねぇが、人の物を盗る方が余っ程悪いぜ」 「旦那の仰る通りだ。余りのひもじさについ手が出てしまった、面目無い。そこで相談じゃが拙者とっておきの話を聞かす からその代償に握り飯を一つ戴くと言うのはどうかな」 意地でも恵んでくれとは言いたくないらしい。 「どうせくだらぬ法螺でも抜かすんだろう」 「拙者は若い頃、獲狙(えぞ)を出て武士になるため江戸を目指したが、路銀を使い果たし月館藩に転がりこみ武士になっ たんだが、出世も覚束ず獲狙へ帰ろうと方々彷徨った挙句この峠に棲みついたって訳さ」 「もういい、わしも爺の寝言に付き合ってられねぇんだ」 萬造は腰を上げ発とうとした。 「まぁ聞きなせぇ、」この峠に棲みついて二十年、人間様に出会う事はなかったが一年前、二人連れの男女がこの峠に現わ れたんじゃ」 蛭蔵の話が講談めいてきた。 ――一年前と言えば小夜姫様と茂市の亡骸がこの峠で見つかった頃ではないか。 萬造は立ちかけた腰を再びおろすと、思わず身を乗り出した。 「その二人とは誰なんだ!」 「やっと聞いてくれる気になったようだな」 蛭蔵はにやりと笑い腰の握り飯に視線を移す。 「あの日は大雨が降ってな、わしは寝座(ねぐら)にしている洞穴に駆け込もうとしたのだが、その二人が先に入っておっ たのじゃ。武士を捨てて以来すっかり臆病になったわしは追い出す事も出来ず、木陰に身を隠し様子を窺っておったと 思いな、突然の落雷に肝を冷やしたもんじゃ」 「おめぇの事はどうでもいい、二人はどうした」 「そう慌てなさんな、雷が静まり再び洞を覗いたわしは其処に信じられない光景を見たのさ」 蛭蔵はにやにやしながら勿体ぶってみせる。萬造は苛々してきた。 「この野郎!言いたくないならもういい!」 「言うよ、言うから握り飯を一つ呉んねぇか」 「何だ、これが欲しいんならみんな呉れてやるから話を続けろ!」 風呂敷ごと抛ってやると蛭蔵は瞬く間に三個の握り飯を平らげてしまった。 「二人が抱き合ったのは落雷が怖い為だと思ったがそれだけでは無かった。互いに口を吸いあったり重なって呻いたり、 見ていられなかったぜ」 「爺ぃ!ふざけるな!」 萬造は爺の作り話に乗せられ、まんまと握り飯を盗られたような気がしてならない。握り飯は惜しくはないが、小夜と 茂市だと見当をつけ聞いていたのだが二人が乳繰り合うなどあろう筈も無い。爺の話に乗せられた自分に腹が立つ。 「旦那が嘘だと思うのも無理は無ぇ、わしとて信じられねぇ光景だったもんな。しかも男は腰元風の女を姫様と呼んでたし 駆落ち者でもなさそうだったがな」 「何?姫様だと?」 「確かにそう呼んでたな」 萬造は信じたくなかったが、最早蛭蔵の話を聞き流す事は出来なかった。 「それで話は終りだな」 「その後、若者が自刃し、腰元は塩根川へ身を投げた。わしは咄嗟に駆け下り塩根川から腰元を掬いあげこの洞まで運んで やったのさ。尤もその二人も馬に乗った武士が大勢で来て連れていったがな」 蛭蔵は此のあと、朴の葉に穴が空いてるのを指しながら、姫と呼ぶ腰元に詫びながら体を重ねた茂市の哀れさをこう語った。 「若者は朴の葉を腰元の腹に乗せ赦しを請いながら体を重ねたんじゃ。あの朴の葉は何を意味したのかな。あれ以来朴の葉に 無数の穴が空いた事を考えると無性に人の世が儚く思えるのさ」 * * * 「茂市の馬鹿野郎!」 峠を転げるように萬造が駈けて行く、湯女沢の妹のことはすっかり忘れていた。 「畜生!ちくしょう!」 何に対する悪態かも定かでない罵声が口を突く。今更この事実が世に広まれば小夜姫の名声は失墜する。かといって萬造 一人の胸に収めておけ程安易なことでは無かった。 ――取り合えずご領主様にお伝えしよう。 萬造は高堂楯目指して走りに走った。 「ご注進!ご注進!」 萬造が高堂楯の門を叩いた。 「何事か!」 声を聴きつけた相良甚内(側近)が問う。 「急ぎ御報せしたき一大事で御座ります」 「よし、通れ」 萬造は常々高堂楯の伝言板のような役割を果す敏忠の懐刀である。一大事と聞いて甚内は即座に敏忠の元へ同行した。 敏忠は萬造の話を黙って聞いている。話が終っても何かをじっと考えているようだ。 「萬造、この話誰かに漏らしたのではあるまいな」 「いえ、先ずはお殿様にご注進と思いまして駆けつけまして御座います」 「この事、忠頼様へ申し上げご指示を仰がねばならぬ、他言無用に願いたい」 「勿論その積りで御座います」 この悲話は蛭蔵――萬造――敏忠――忠頼 と伝わり終止符が打たれたものの、蛭蔵を野放しにした事が新たな火種と なり、巷に広まっていった。然し、この噂は小夜姫の純愛話として領民の心に刻まれ、峠の名も塩根坂峠(塩根川に 因んだ名前)から主寝坂峠(主と寝た坂)と変り、悲恋を哀れむ「哀憐峠」とも称ばれるようになったのである。 |
| 主と寝たのか 主寝坂峠 朴の葉に何かの跡がある 悲しき性に 身を焼かれ 逝きし小夜姫 哀れなり 主と下僕の しがらみに 斃れし茂市も 哀れなり 主寝坂峠は 哀 憐 峠 |

【この物語は昔父に聞いた伝説を基にアレンジしたフィクションです。主寝坂峠に纏わる伝説は峠を挟む山形県と秋田県では
登場人物や脚色が若干異なりますが、身分の差を埋める条理の証として朴の葉が用いられたこと、塩根坂が主寝坂に変った
のも、この伝説が基になってるとの言い伝えは今も変らず残されています。尚、地元の人は「主寝坂」を ”しぉねざか”と
発音するところからも<塩根>が<主寝>になったと言う説は見逃せません。山形県金山町外沢字主寝坂との村落は平成初
期まで人家が存在しましたが、現在は移住し地名だけが残っている状態です】
| 哀憐峠クリック順1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 |
| 段々長く | 絵回文 | 気紛回文 | 漫画回文 | 野球迷鑑パ | たいこめセ |