|
|
| 哀憐峠クリック順1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 |
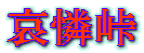

| 神室忠頼は廻廊に立ち空を眺めている。 「雨も上がったようだな」 「はい、落雷が雨雲を吹き飛ばしたように御座ります」 掃部が側で答えている。 「落雷は高堂のあたりかな」 「その先の塩根坂峠のようでもありました」 「小夜姫は無事蟻谷関(「アリヤゼキ」*別称を羽の関とも言う)を越えたのであろうな。この雨で難儀してるのではなかろうか」 「その事ですが、姫様はまこと湯沢へ向われたのでしょうか」 掃部は恐る恐る忠頼の顔色を窺う。 「何故じゃ?」 「はい、姫様が蟻谷(ありや)関を通る事があっても、咎め立てせぬよう今朝ほど早馬を発てたのですが、その者が 先程帰って参りまして、姫様らしきお姿は通らないとの事でした。湯沢に参るには他に道も御座いませぬ。もしや 未だ領内の何処かに居られるのではないかと・・・」 「それで領内を探ったと申すか」 「いえ、探りは致しませぬが、何処に居られるのかと案じておりました」 「午の刻も過ぎたと言うに行方が知れぬとは確かに面妖、手分けして密かに探ってくれるか。但し居所が判明しても 連れ戻す事はせずに、遠くから見守るのだ。よいな」 「ははっ、心得ました」 掃部が引き下がるのと入れ違いにお甲が美濃紙を一枚持って駈けてきた。 「お殿様、姫様のお部屋にこの様な置手紙が御座いました」 ――遺書ではあるまいな・・。 一瞬不吉な予感が忠頼の脳裏を過った。美濃紙にはこんな歌が書かれている。 くもはきゆさわたつしろのとおけれと かなしみくらしさよにつきなく これを漢字書きにすれば 雲は消ゆ騒立つ城の遠けれど悲しみ暗し小夜に月無く とでもなるのだろうか。 <訳> 空は晴れお城の騒動も遠く過ぎ去ったけれど、悲しみは癒えず無月の暗さのようです こんな解釈にも取れる和歌である。 忠頼はそこにもう一つの心を見ていた。 くもはきゆさわたつ → 苦も吐き湯沢発つ (苦しい事は捨て湯沢へ発ちます) しろの とおけれと → 城の 遠けれど (城は遠くなるけれど) かなしみ くらし → 哀しい生活(くらし)は忘れます さよに つきなく → <誰が悪いのでもなく>小夜にツキ(運)が無かったのですから <要約> 「苦しみも捨て湯沢へ発ちます。城を出て行きますが誰をも恨みません。全ては小夜の運命なのです」 忠頼の胸にこみ上げるものがあった。 「小夜は矢張り湯沢へ発たれたのだ、それにつけても蟻谷関を通らずに何処を越えようというのだ」 小夜と茂市が塩根坂峠を越えようとした事や、狂おしき抱擁を繰り広げたことなど、忠頼ならずとも想像 出来ぬことである。 「殿!嬉野、那呵田郷を探索した者が戻って参りました」 掃部があたふたと駆けつけ意気込む。 「そうか、直ぐ参る!」 ――よい報せであればいが・・。 胸騒ぎを抑え庭へ向う。 「どうじゃ、姫は見つかったか」 急き込む問いに徒頭(かちがしら)の一人が答える。 「姫様のお姿は有りませんでしたが、今日の明け方那呵田の農家で背負子を借りた若者がいたそうです。連れの女は 腰元風だったそうで、駆落ちでもするんだろうと見逃してやったそうです」 「それが小夜姫と茂市だとでも言うのか」 「定かではありませんが、背格好、風貌などが似ております。又腰元風と言うのも姫様がお城を発たれた時の出で立ち に類似するものがあります」 「成る程、して其の両名は敏忠殿の目にも止ったのであろうな」 「いえ、何しろ夜も明け切らぬ寅の刻の事とて見た者はその農民だけでした」 「未明のことなればそれも已む無しか。話の様子から小夜と茂市の二人のようだが、那呵田の先にあるのは塩根坂峠、 深窓で育った小夜がどうやってあの剣山を越えようというのだ」 信じ難い事ではあるが、小夜の残した歌や徒頭の話から推して二人が峠を越えようとしていた事は間違いないようだ。 いや、もう既に湯沢へ辿り着いているのかも知れなかった。 「無事に越えられたのならそれも良し。探索は打ち切りあとは無事を祈ろうではないか」 忠頼は神室山に向かい合掌した。 「無事であってくれ」 そう祈る心とは裏腹に一抹の不安を時折頭をよぎる。それはあの剣山を越えられるのかとの疑念である。 ――余に心を開かずともよい。側に居てくれ。 小夜の前にひれ伏したい程の衝動が忠頼の胸を掻き毟る。その恋情を表に出すことの出来ぬもどかしさ、儚さが峠の 崖と闘っている小夜の影と重なり泪が出そうになる。だが家臣の前では気丈に振舞うしかない忠頼なのだ。 弥太郎との真剣勝負を告げられても、共に笑ってそれに従い、これが武士の運命だと割り切れた程の忠頼も、小夜との 不本意な別れに表に出せない動揺が心の波を荒立たせていたのである。 初めて失踪を聴かされた時、湯沢へ行くには当然蟻谷関を越えるものと考え小夜と隔たる寂しさはあれど然程の動揺 は無かった。それが塩根坂峠を越えようとしている事を知った時から動揺の度合が急速に広がったのである。 ――自分は姫にとって親の仇でしかない。・・・そんな負目が忠頼に消極的な判断を迫り、悪しき方へ変遷してゆく。 若し、失踪と同時に追手を差し向けていたとしても、塩根の峠を越えるとは思わなかっただろうし、小夜と茂市を探せ たかは疑問であるが、展開は変っていたかも知れない。然し、全てが運命に操られていく人の世に ”若し” と言う過去 は存在しない。 失踪から五日が過ぎた。城下は麦穂の黄と植田の緑に調和され、穏やかな日和である。忠頼は廻廊に佇ち麦秋の野を 見渡し其の目を、遥かに霞む塩根坂峠に移してゆく。 「あの日の落雷は彼の峠だったとの事、まさか落雷に撃たれたと言うこともあるまいが、この胸騒ぎは何としたことか」 小夜姫が無事湯沢に着いたのであれば、そろそろ何らかの便りがあってもいい頃なのだが未だその気配もない。忠頼は 義康惨殺から城主になった経緯など、龍興(湯沢城主)には弁解がましくなるのが嫌でこれまで何も話してなかったが、小夜 の安否も含め書状を認め(したため)早馬を送ることにした。 「掃部、掃部はおらぬか!」 「はい、如何なされました」 「硯を持って参れ、湯沢へ早馬じゃ早々に用意せよ!」 「承知しました。一体何が有ったのですか」 「訳はあとだ!早くせぃ!」 「ははっ」 掃部は慌てて硯を取りに走る。 「龍興殿に書状を認める間に馬の用意を頼む」 忠頼は些か不安を覚えながら書状を認める。掃部が次の指示を待って畏まっている。 「この書状を湯沢城に届け龍興殿の返事を戴いてくるのだ」 城一番の使い手、疾風平九郎が書状を懐に湯沢城へと馬を駆ってゆく。比羅保許から湯沢までは凡そ十八里、早馬を 飛ばせば一刻半の道程である。 湯沢城では龍興が松の盆栽を並べ手入れに余念がない。 「はてな、松葉に精彩が見えぬが、三日前の驟雨で潤った筈なのに水が足りなかったかな。」 訝りながら如雨露を手にした時、後ろで庭番の声がした。 「殿、比羅保許城より使者に御座います」 龍興の肩がピクリと動いた。松の萎えに不吉な予感を覚えたからである。若い頃には神仏や迷信などは信じなかったのに 齢と共に験(げん)を担ぐようになっていた。 「疾風平九郎、わが殿よりの書状を持参仕りました。ご返事を賜りとう御座います」 「ご苦労であった。返書を認めるまで暫し休息されよ」 使者より書状を受取り読みすすむ龍興の目は血走り、顔面は蒼白となってゆく。その書状には弥太郎・敬四郎の果し合いに 始まり、義康惨殺の一件、城主拝命の趣旨、小夜姫失踪までの顛末が綿々と綴られていたのである。 果し合いや惨殺の 件(くだり)には無い筆の乱れが小夜姫失踪の件では急に乱れ、泪の跡さえ見えるのを龍興は見逃さなかった。 ――忠頼殿も辛かったであろうな。 龍興は弁明もせず、あからさまに事実だけを述べている忠頼の心情に胸を熱くしていた。 巻末は 姫が湯沢城を頼られ城を出られしが無事到着なされしや否や 姫の心情を鑑み駕籠は基より 供の者さえ配する事なく出立なさしめたるは忠頼が浅慮なり わが仕打ちにお腹立ちあらば 龍興殿の手に懸り討たるるも已むなき仕儀に御座候 比羅保許城主 神室忠頼 と結んである。書状を読み終えた龍興の顔は平静さを取り戻し、平九郎を呼んだ。 「使いの儀、ご苦労であった。書状を認めるまでもない。明日には余が比羅保許を訪れ見(まみ)えるとしよう。小夜姫は まだ到着せぬが、女子(おなご)の足なればまだ着かずとも心配いらぬ。迎えの輿を用意して手配したから安心せいとな」 「ははっ、心得まして御座ります」 平九郎を帰し再び盆栽の手入れに向った龍興は呆然と突っ立った。 「こ、これは何とした事か!!」 早馬の到着から半刻も経たぬと言うのに。松は葉を落し哀れな姿で枯果てていたのである。 「小夜の身に異変があったに相違ない!」 鉢を地面に叩きつけ庭をあとにする。微塵に砕け散った鉢と枯松に暗雲が漂う。 「騎馬隊二十名を連れ比羅へ参る、即座に出発じゃ!」 一刻のち、騎馬隊を従えた龍興の一行は羽の関を越えていた。 「戦だろうか」 蟻谷関の番人はおろおろと見送るばかりである。 「戦にしては二十の騎馬隊とはおかしいな」 「湯沢のお殿様は前触れもなく戦を仕掛けるようなお人ではない、下衆(げす)の勘繰りは止せ!」 御番所頭が狼狽を見せまいと声高に制している。 程なく騎馬隊は比羅保許城の門を叩いた。 「湯沢城主清沢龍興、火急の用有って神室殿に逢いに参った。門を開けられぃ!」 龍興の大音声に門番が慌てて門を開く。平九郎が帰って半刻も経たぬ龍興の来訪に忠頼は驚きはしたものの、狼狽える ことなく鄭重に迎え入れ、龍興を上座に据え自らは下座に畏まった。 「火急の事なれば無礼は赦されぃ。書状によれば余を頼って小夜が失踪と聞き、明日出向く筈だったが、枯れる筈もない盆栽 の松が半刻の間に枯れたのを見て何かの暗示と思えてこうして参った次第、詳しく話して呉れぬか」 「頼(より)もそれが気懸りで失礼を省みず書状を認めた次第、ご無礼致しました」 「その事はよい。して何か手懸りは?」 「書状にも認めました通り、頼は姫にとって親の仇、手を差し伸べても受け入れてはくれまいと追手も向けず、さりとて 中間一人の道連れでは心もとなく後を追わせしも行方知れず、ただ無事に湯沢へ着く事を祈るだけでした」 「行く先が余の城とどうして知れた」 「姫の遺された歌と探索に当った者の言より推して間違いなきものと存じます」 「湯沢に向うには羽の関を越えねばならぬが、確かに関所は通ったのだな」 「それが連れ戻される事を考えてのことか、塩根坂峠を越えた様子に御座ります」 「何!!塩根とな。道とて無きあの剣山を深窓で育った小夜が無事に越えられると思うてか!」 「定かではありませぬが。されど探索に当てた者の話から推して他には考えが及びませぬ」 「小夜の遺した歌を見せて貰えぬか」 「これで御座ります」 忠頼は自ら座を立ち、美濃紙を取り出し渡した。一城の主と雖も龍興と忠頼では格が根本的に違った。しかも忠頼には 小夜を失踪にまで追い込んだとの負目がある。今は龍興の家臣にも均しき忠頼である。 くもはきゆさわたつしろのとおけれと かなしみくらしさよにつきなく 小夜の悲しみが滲むような仮名文字の流れが泪を誘う。 雲は消ゆ騒立つ城の遠けれど・・・・ 幾度も読み返すものの、龍興にはこの歌から湯沢と言う文字が見えてこない。野武士から一城の主に登り詰めた龍興は 歌に疎いところが有り、懸詞(かけことば)の裏が見えてこないのだ。 「この歌が湯沢へ向う事を伝えていると言うのか」 「さすれば、上の句、くもはきゆさわたつ(雲は消ゆ騒立つ)は ”苦も吐き湯沢発つ”とも読めます。姫は ”苦しみは忘れ湯沢へ発ちます”と言いたかったのだと存じます」 「余は歌の決りもよう判らぬが忠頼殿からそう聞けば頷ける。よし、塩根を軸に小夜の消息を探るとしよう依存は御座らぬか」 「ははっ、有り難き幸せ、頼が至らぬばかりにご雑作かけます」 「その事はもう良いと申すに、そうと決れば出発じゃ」 龍興配下、騎馬隊二十名。忠頼配下、騎馬隊三十名、徒兵五十名。総勢百名の捜索隊が塩根坂峠を目指し那呵田へ差掛った。 その行く手を十名の家来を従え高堂楯宰相、厨田敏忠が阻んだ。 「平九郎殿より小夜姫様探索と承り、お待ち致しておりました。微力ながらその列に吾らもお加え下さい」 「かたじけない、然らば塩根坂峠は湯沢から参った吾等は地形に疎い。道案内を頼む」 総指揮を任された湯沢城の騎馬隊長、太政正則(だいじょうまさのり)が馬上より頭を下げた。 「心得まして御座ります。さすれば日暮れも近きことなれば、急ぎ参られましょう。皆の者急げぇ!」 普段は静かな高堂楯に突如現われた騎馬隊に驚く村人を尻目に小夜姫探索隊は西へ向って走り出した。それは那呵田の村人 にとって、青天の霹靂とも言うべき恐ろしき出来事のように映った。しかしその心の底には、姫の無事を祈る庶民の優しさが 込められていた。 (つづく) 9−10 小夜姫探索 終り |
| 哀憐峠クリック順1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 |
| 段々長く | 絵回文 | 気紛回文 | 漫画回文 | 野球迷鑑パ | たいこめセ |