| 段々長く | 絵回文 | 気紛回文 | 漫画回文 | 野球迷鑑パ | たいこめセ |
| 段々長く | 絵回文 | 気紛回文 | 漫画回文 | 野球迷鑑パ | たいこめセ |
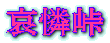
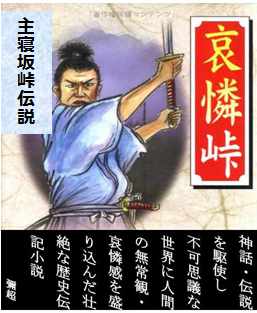
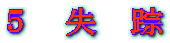
| 小夜姫が父の仇であるべき敬四郎に城主の座を懇願したには理由がある。それは、比羅保許領、延いては村人の 安寧を守るには文武に長けた宰領が必要であると判断したからなのだが、父も亡き今、敬四郎の側に居ることが苦痛 であり、心の片隅に恋慕の情を隠しながら生活(くらし)てゆくのは亡き父にも後ろめたさを感じるのである。父は 湯沢城主・清沢龍興(きよさわたつおき)と親交が深く、小夜も父のように慕っていた。小夜は城の状況が落ち着いたら、 湯沢城を訪れ世話になろうと密かに決意していたが、誰にも胸の内を知られたくはなかった。 「まぁ姫様、今朝はお食事をお召し上がりになりましたのね」 お甲は驚喜の目を小夜に注ぎわが事のように喜んでいる・ 「新しいお殿様もお決まりですし、小夜もいつまでも沈んでいてはお甲に嫌われてしまいますからね」 「まぁ姫様ったら嫌ですわ、お甲がいつ姫様を嫌いましたか」 「あらあら、怒らせてしまったようね。ほんの冗談ですよ」 「怒ってませんよ、嬉しいんです。姫様の笑顔は何十年ぶりかしら」 「お甲さん、十七歳の娘に何十年は酷いですよ」 「冗談のお返しですよ」 「まぁ・・オ・ホ・ホ・ホ・ホ」 明るく振舞う姫の仕種にお甲も上機嫌であった。 「お殿様はお名を変えられたそうですね」 「はい、神室忠頼様となられました」 「小夜もご挨拶しなければなりませんね」 「そうしてください」 「腰元の衣装を準備出来ませんか」 「できますが、どうなさるのですか」 「父も亡き今、私は姫ではありません、忠頼様の御前には腰元としてご挨拶したいのです。 「そこまでしなくても・・・姫様は何時までも姫様ですよ」 「小夜はそうしたいのです」 「判りました」 「誰にも知られないよう頼みます」 「はい」 お甲は部屋を下がりながら又しても泪が出てくる。生まれながらにして薄幸な運命を背負った小夜をわが子のよう に慈しんできたのだが、お甲には父を失った小夜の嘆きをどうすることも出来ないのである。 「姫様の気のすむようにして差し上げるしかできない」 お甲は泪を拭き腰元部屋へと急いだ。この時 ”小夜の食欲が急にすすむようになった事” や ”腰元の衣装を誰に も知られずに” と言う言葉に疑問を抱いていれば次に起こる悲劇は防げたであろう。たが小夜を哀れと思うお甲の純心 が小夜の為に尽そうとする余り盲点を気付かせるまでに至らなかったのである。然し、お甲を責める事は出来ない。 無月の夜、忠頼は書斎に籠りこれからの藩政に必要な文献を繙いていた。隙間風なのか、燭台の焔が揺らぎ消えた。 「殿!一大事で御座います!」 暗がりに足音をばたつかせ家老の楳図掃部が駆け込んできた。(城主が変わり刑部は隠居、掃部が主席家老となる) 「夜更けに何事じゃ!」 「小夜姫様のお姿が見当たらないとお甲が騒いでおります」 「何っ?姫がどうしたと言うのだ!」 消える筈の無い灯りが消えたのは不吉な報せだったかとの胸騒ぎを覚え、忠頼は内心穏やかでない。 「どうやら城を出られたようにござります」 「何っ!失踪したと申すのか!」 「はっ、そのように御座ります」 「して、供の者は?」 「中間の茂市が見当たりません、奴が一緒に出たかと・・・」 「そうか、どうやら失踪は確からしいな。姫が頼れる所と言えば高堂楯か湯沢城、然し覚悟の上で城を出られたと すれば、直ぐに連れ戻される高堂楯では無い。矢張り湯沢の龍興様の所だろう」 「羽の関に先回りして連れ戻しますか」 「いや、父上を殺めた余が城主では姫もお辛いのだろう。そっとしておけ」 「承知しました、深夜の醜態ご無礼致しました」 「そちのせいではない、気にするな」 「ははっ」 楳図掃部が下がり床に就いた忠頼は寝付かれず小夜の身に思いを馳せていた。 ――思えば姫には不憫なことをした。武士の意地もあり殿を殺めたことへの後悔はせぬが、わしとて心痛むものが ある。さりとてわしが手を差し伸べても受け入れては呉れまい、所詮わしは姫にとって親の仇なのだ。 気丈な忠頼の目に泪が溢れ枕を濡らす。あの愚策(婿選び)さえ無かったら喜んで姫を迎え入れたであろうに今は それも叶わぬ夢である。小夜が望むのならばと享けた城主の座が小夜を失踪に追い込み、忠頼の心とは裏腹に変転 していく時の流れに、武士の意地と言うものが如何に無力なものだったかを噛み締めている忠頼でもあった。 「姫様、城では失踪に気付き既に追手を差し向けたものと思われます。羽の関に向えば直ぐに連れ戻されましょう。 雄岳薬師山を迂回し、宝山(ほうやま)嬉野(うれしの)甲蝉(こうせみ)那呵田(なかだ)を経て塩根坂峠を越える意外抜け 道はありませんがご辛抱願います」 小夜の手をしっかりと握り締め茂市の足は剣山の塩根坂峠へと向っていた。今にも追手が来そうで犬の遠吠えにも心 が急く。小夜の足からは白い足袋を赤く染め血が滲んでいた。 「姫様、少しお休み下さい」 宝山を過ぎ、嬉野を出た所で茂市は傍らの石に小夜を誘(いざな)った。 「那呵田まではあと一里、塩根坂峠までは一里半の道程です」 血の滲んだ足袋を脱がせ手当てをしてやりたいが、下僕の身で貴き姫の素足を見ることなど出来る筈も無い。茂市は 心を鬼にしてでも峠越えを成功させようと心に誓った。 「姫様、お辛いでしょうが夜明けまでに塩根坂峠まで参りとう御座います、ご辛抱の程を・・・」 四半時(30分)程の休憩で少しは疲れも柔らいだとは言え、小夜には酷な旅である。然し忠頼の気遣いを知る由も無い 茂市には峠を越えねば湯沢へ辿り着くことは出来ぬとの信念が邪魔をしていた。来る筈も無い追手に怯えながら、那呵田 に辿り着いた茂市は、とある農家を訪い背負子(しょいこ)を借り先を急いだ。 塩根坂峠は御徒岳(おかちだけ)の西側に位置する山で人跡未踏の霊山である。御徒岳と塩根坂峠との間には野削(のそぎ) と言う集落が有り、僅かな稗と粟を頼りに生活(たつき)を営む寒村である。御徒岳から流れ出る地水が清流となり野削の 村を潤し流れてゆく。この清流を塩根川と言い、それに因んで名付けられたのが、*塩根坂峠である。道らしきものと言 えは狐狸や熊などが歩いた獣道だけである。深窓に育った小夜姫がこの剣山を越えようとは忠頼でならずとも想像も絶す る事であり、それが又茂市の狙いでもあった。追手に怯えながら塩根坂峠のとば口に立つ頃には朝日も尾根を離れ、汗ば む程の陽射しとなっていた。小夜は比羅保許城と思しき方角(かた)を振り返り両手を合わせ別れを告げた。 「もう二度と帰る事は許されないのね」 小夜は必死に泪を堪えようとするが、その瞳に父や敬四郎(忠頼)の顔が重なり堪えきれずに顔を覆ってしまう。茂市も 又そんな小夜の姿に泪していた。 「姫様、ここからは難所に御座りますれば、身共の背にお掴まりください」 茂市は背負子の背を小夜に向けた。 「雑作をかけます」 一瞬躊躇いを見せた小夜だったが、眼前に聳える剣山を自力で踏破することは叶わぬと観念してか背負子の荷となった。 屹立する剣山を前にして、追手の幻惑からくる茂市の怯えは消えていた。これから越えねばならぬ峠の険しさが全ての 雑念を寄せ付けなかった。 ――姫様を湯沢へお連れする為にこの命、冠露山(かむろ)の神に捧げ奉る!。 心で誓い、一歩一歩確かめるように坂を登り始めた。粘土質の斜面は滑り易い、茂市の足は鶴嘴となり幾度もその斜面 を突き刺した。茨を薙ぎ熊笹を払う両の腕はさながら鎌の如く、その形相は阿修羅と化した。 ――芥にも均しきこの命尽きるとも、姫様のお命守り通さずにおくべきや。 茂市の執念は二刻のち峠の頂上を極めていた。 「姫様、あれが野削の里、右手の清流が潮根川、その後方に聳えるのが御徒岳で御座います。あの峠を越えれば湯沢は目 と鼻の先、夕方には到着出来ましょう程にもう暫くのご辛抱を」 茨や岩に傷つき満身創痍の茂市だが小夜に不安を持たせまいと明るく振舞っている。 「そなたには苦労かけます。湯沢に着いてからもずっと小夜の力になっておくれかえ?」 小夜は労うように言葉を返した。 「勿体のう御座います。茂市は一生姫様のお側でお仕えしとう御座います」 ”頼りにされている” との満足感から傷の痛みなど毛ほどにも感じていない茂市である。感無量の域に浸りいる茂市の 耳は微かな遠雷の音を捉え振り返った。西空は墨を流したような暗さの中で雨を降らし、この峠に達するまで幾許の刻を 要さぬかに思える。 「いかん!大雨がくるぞ!」 山上での大雨は危険が伴う。茂市は慌てて雨を凌げる場所を物色する。幸い数間程の距離に朴の老樹が枝を広げその 根方が朽ちて洞(うろ)を象っているのが見える。 「姫様、大雨が来ます、一先ずあれへ参られませ」 姫を誘い洞へ駆け込む。背を追いかけて驟雨が峠を覆った。洞の中は薄暗く二畳程の広さに枯木や草が敷かれ人間の 手が加えられた風にも見えるが、人跡未踏の峠に人が棲む筈もなく、熊の寝座(ねぐら)のようでもあり不気味である。 (*註・塩根坂峠は伝説により主寝坂峠と名が変わり、現在も国道13号線のパイプ役を果している) (つづく) 5 失踪 6塩根坂峠 終り |
| 段々長く | 絵回文 | 気紛回文 | 漫画回文 | 野球迷鑑パ | たいこめセ |