| 回文塾 | 初歩回文 | 俳句回文 | 元旦干支 | 県花県名 | 都道府県 | 時事報道 | 源氏絵巻 | 短編小説 | 23区詩歌 |
| 回文塾 | 初歩回文 | 俳句回文 | 元旦干支 | 県花県名 | 都道府県 | 時事報道 | 源氏絵巻 | 短編小説 | 23区詩歌 |
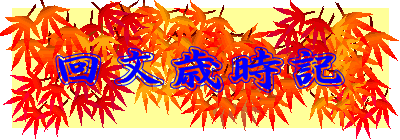
俳句回文は含蓄のないものになることは知らない訳ではないが 敢えて季語を入れた
回文に挑戦してみた 中七の臍語で折返すには四文字以上の季語が使えない事もあり
正規の俳句を詠む場合と比較して格段に難しい事も解った 短歌であれば内容も少しは
伴うのだが短歌には季語など必要がない 取り敢えず愚作ながら回文廃句をご覧あれ
| 季 語 | 【新 年】 | 季語の説明 |
| 元 旦 | よみなれはがんたんたんかはれなみよ 詠み馴れは 元旦短歌 晴れな御代 |
元日の朝 「元」は始め 「旦」は朝(あした)の意 |
| 新 年 | ながきんがしんねんねんじかんきかな 汝が謹賀 新年念じ 歓喜かな |
年の始め |
| 去 年 | こぞのけを のぞきよきその おけのそこ 去年の卦を覗き良きその桶の底 |
去年今年(こぞことし)の季語から分別使用され 「過ぎ去った年を顧みる心」で新春の季語とされている |
| 今 年 | ことしきき にたりはりたに ききしとご 今年嬉々似たり張田に聴きし吐語 |
去年今年の季語から去年・今年と分別して季語とした もの 新年の意もある |
| 初 日 | いくるかびはつひのひつはひかるくい 生くる華美初日の筆は光る句意 |
元朝の日の出 初日の出 |
| 屠 蘇 | みずてんの とそひるひそと のんですみ 見ず天の屠蘇昼ひそと飲んで澄み |
年頭に用いる薬酒で延命長寿の縁起もの |
| 初 春 | みなとおしのるはつはるのしおとなみ 港圧し 乗る初春の 潮と波 |
陰暦正月は春の始めなので初春と言うが、正月と言う 意味で陽暦にも新年の季語として用いられる |
| 若 水 | くむおだきわかみずみかわきたをむく 汲む小瀧若水三河北を向く |
元日の朝一番に汲む縁起もので年男の役割とされている |
| 鳥 追 | かびためしとりおいおりどしめたひか 佳日試し鳥追折戸閉めた日か |
東北や信州で行う農村正月行事 鳥を追い払い豊作を 祈願する |
| 書 初 | しなれたみかきぞめぞきかみだれなし し慣れた身書初ぞ机下乱れなし |
年が改まり始めて書や絵を書くこと 一月二日 【書初見本】 新玉の年の始めに筆執りて萬の宝書くぞ集むる |
| 独 楽 | まごひまごいろじはしろいこまひごま 孫曾孫色地は白い独楽緋独楽 |
正月に子供たちが遊ぶ玩具 ひねり独楽 ばい独楽 うち独楽 など |
| 出 初 | でぞめましはれぎをきればしまめそで 出初増し晴着を着れば縞目袖 |
消防士の初出勤の儀式 一月六日に全国的に行われている |
| 初 卯 | こいたれば はつうにうつは はれたいこ 請い足れば初卯に打つは晴太鼓 |
正月最初の卯の日に神詣することで 御嶽神社 石清水八幡宮 賀茂神社などが有名 |
| 初 巳 | びのきんがはつみにみつはかんきのひ 美の謹賀初巳に満つは歓喜の陽 |
正月最初の巳の日に弁財天に詣でること |
| 初閻魔 | まんえつはよきひのひきよはつえんま 満悦は良き日の悲喜よ初閻魔 |
正月十六日 閻魔の初縁日 この日とお盆の十六日(やぶいり) は地獄の釜の蓋も開くとされ奉公人の里帰りが許される日でもある |
| 季 語 | 【春 季】 | 季語の説明 |
| 余 寒 | えみなるはよかんさんがよはるなみえ 笑みなるは余寒山河よ榛名見え・ |
寒が明けてから尚残る寒さを言う |
| 淡 雪 | よきしなかきゆはあはゆきかなしきよ 予期し中消ゆは淡雪哀しき世 |
春に降る雪で解け易く湿っぽい雪 |
| 春の日 | せはまるくはるのひのるはくるまはせ 背は丸く春の日乗るは車馳せ |
春の日差し 又は春の一日を言う |
| 暖 か | かびしりて かただあたたか てりしひか 佳日知りて過多だ暖か照りし陽か |
暑くもなく冷え冷え感もない日差し |
| 霞 | みなきろもかすみはみずかもろきなみ みな帰路も霞は見ずか脆き波 |
一般的に微かな霧状の集まりを霞と言い遠目に見える 薄雲のようなもの 霞は春 霧は秋の季語とされている |
| 初 午 | かねみっつはつうまうつはつづみねか 鐘三つ 初午打つは 鼓音か |
旧二月に稲荷神社を詣でる祭礼 |
| 長 閑 | かきのえだのどかなかどのたえのぎが 柿の枝 長閑な門の妙の戯画 |
空が晴れてのんびりとした感じの天気を言う |
| 桜 | けさにちち さくらひらくさ ちぢにさけ 今朝に遅々桜開くさ千々に咲け |
三月から四月にかけて南から順に北上する国花 咲いてから三・ 四日で散ってしまうので潔い花とか哀しい花と見る人もいるようだ |
| 剪 定 | そうろともいてんせんていもどろうぞ 走路とも移転剪定戻ろうぞ |
庭木や果樹園などの枝を切り取って新芽が出やすいようにする作業 |
| 花 見 | うまざけをはなみのみなはおけさまう 旨酒を花見の皆はおけさ舞う |
主として桜を見ながら飲食することを言う |
| 雁風呂 | でしにこじ がんぶろ ぶんか しごにして 弟子に古事雁風呂文化死語にして |
雁が北帰した後の浜辺で小枝を集め風呂を焚いて雁を 供養したという伝説から生まれた季語 |
| 春 雨 | かねのおとはるさめさるはとおのねか 鐘の音春雨去るは遠の嶺か |
春に降る雨 豪雨ではなくどこか憂いを誘うような雨 |
| 日 永 | たえなるを きかなひながき おるなえだ 妙なるを聴かな日永き折るな枝 |
冬至以後は畳の目一つずつ日が伸びるそうだが春は暖気と共に 日が永くなったと感じられる 他に「日脚伸ぶ」との季語もある |
| 彼 岸 | くさのなはひがんらんかびはなのさく 草の名は彼岸蘭華美花の咲く |
春分を中日とし前後三日ずつ計七日間を言う |
| 春の月 | きつのるはねふりつりふねはるのつき 来つ乗るは根振り釣舟春の月 |
春の月 わけても満月は橙色を深めてぼってりと重い |
| 貝寄風 | しきりくめかいよせよいかめくりきし しきり酌め貝寄風酔いか廻りきし |
陰暦2月聖霊会の頃に貝を岸辺に寄せる風を指して名づけられた |
| 春北風 | みなしくにたきるはるきたにくしなみ みな頻くに滾る春北風憎し波 |
春北風(はるきた・はるならい)と読む 晩春の北西風 (春寒) |
| 逝く春 | よるなぜか くゆはるはゆく かぜなるよ 夜何故か悔ゆ春は逝く風なるよ |
春の季節の終わりを惜しむ表現・(行く春) 対象語→惜春 |
| 季 語 | 【夏 季】 | 季語の説明 |
| 初 夏 | くらぶそか しょかなながよし かそぶらく 比ぶ楚歌初夏な名が佳し過疎部落 |
夏の始め 木々も葉を広げ田植えが始まる五月初旬頃か |
| 夏めく | なだのさけくめつなつめくけさのたな 灘の酒酌めつ夏めく今朝の店 |
吹く風も日差しも汗ばむほどに暖かさを感じる頃 |
| 五 月 | かいごうとごがつはつかごとうこいか 邂逅と五月二十日後訪う恋か |
歳時記では五月を初夏・六月を中夏・七月を晩夏とするが あくまでも陰暦でのこと 陽暦にはそぐわない季語も少なくない |
| 立 夏 | ねふりとも りっかいかつり もどりふね 音振りとも立夏烏賊釣り戻り船 |
二十四気の一つ 陰暦四月の節で陽暦では五月六日頃に当たる |
| 田 植 | こがたいき たうえなえうたきいたかこ 子が待機田植苗歌聴いた過去 |
昭和の中頃まで田植えは六月中旬までかかったように記憶して いるが今は五月のゴールデンウイークがピークのようだ(東北) |
| 鯰 | おかだけはすまないなまずはげたかお 陸だけは棲まない鯰剥げた貌 |
ナマズ科に属する淡水魚 体長は50cmくらいまで成長する |
| 六 月 | かようとほろくがつがくろほどうよか 通う徒歩六月学路舗道良か |
新緑の五月と万緑の七月の間にある六月はどことなく曖昧な感じ だが農家にとっては植田の管理に神経を使う大事な季節でもある |
| 筍 | てもないがたけのこのけたかいなもて 手段も無いが筍退けた腕以て |
「たけのこ」にもいろいろあるが「筍」と書くと孟宗竹を思い浮べ てしまう 笹竹の子は「竹の子」と書くのではないだろうか(笑) |
| 滴 り | さかのづく したたりただし くつのかざ 坂の梟(ずく)滴り正し窟の迦座 |
山の岸壁や蘚苔類から滴り落ちる点滴を指して言う |
| 涼 し | すずしさやかぜなるなぜかやさしすず 涼しさや風鳴る何故か優し鈴 |
涼しいのは夏よりも初秋なのに敢えて夏の季語にしてあるのは暑い 中で木陰や瀧の近くに寄った時に本当の涼しさを感じるからなのだ |
| 夏 至 | さけのみか げしのたのしげ かみのげざ 酒のみか夏至の楽しげ神の下座 |
二十四気の一つ陽暦では六月二十一〜二十二日頃 一年中で最も日の永い一日である (対象語)・冬至 |
| 盛 夏 | さけのみとかいせるせいかとみのけさ 酒飲みと解せる盛夏富の今朝 |
夏の盛り 野山は万緑に覆われ太陽は灼けるほどに暑い ・真夏 |
| 鰻 (真蒸) |
まむしはみ しかにはにかし みはしむま 真蒸し食み歯牙には苦し身は染む間 |
真蒸しは鰻の異称 土用の丑の日は 真蒸し(鰻)を喰い 夏バテを防止する風習は今なお続いている |
| 土用丑の日 | しりあいと ひのしうしのひ といありし 叶う世と日延し丑の日土用中 |
丑の日月毎にあるが、土用の丑の日は一度が二度あり一の丑、 二の丑と区別する。 |
| 出 水 | しらくもよでみずあすみてよもくらし 白雲よ出水明日見て世も暗し |
梅雨どきから盛夏にかけて大雨や長雨で洪水になったりする事で 台風による洪水は含まれない |
| 短 夜 | やみのとやよかしみじかよやどのみや 闇の途や良かし短夜宿飲屋 |
夏は日中が永いので夜が短くなるその上夜も蒸し暑く寝苦しいので 直ぐに夜が明けてしまう 夏の短夜← → 秋の夜長 |
| 季 語 | 【秋 季】 | 季語の説明 |
| 残 暑 | しいとしいざんしょよしんさいしといし 恣意と思惟残暑よ診査医師訪いし |
秋になり未だ夏の暑さが残っている様を言う |
| 爽やか | きしさればがやはさわやかはれざしき 来し然れば雅屋は爽やか晴座敷 |
さっぱりとして快いこと 主観的な季語ではあるが適当に決められ た訳ではない (春の「長閑・麗らか」などもこの類) |
| 新 涼 | よきがなはしんりょうよりんじはながきよ 佳きが名は新涼よ 臨時は長きよ |
残暑も過ぎ本格的に秋が到来すると心地よい涼しさがやってくる そして直きに実りの秋を迎えるのだ |
| 文 月 | しなきいざ きつみふみづき さいきなし 死無きいざ機積み文月再起成し |
陰暦七月の異称でほぼ陽暦の八月上旬から九月上旬の候 |
| 八 朔 | はんせんをはっさくくさつはおんせんば 阪線を 八朔草津は 温泉場 |
陰暦八月一日の異称 「八月朔日(はちがつついたち)」 |
| 九 月 | よみてもよしくがつてつがくしょもてみよ 読みても良し九月哲学書以て見よ |
上旬はまだ残暑が残っているがやがて台風がやってくる九月 ・十月は収穫の秋でもあるが天災に悩む季節でもある |
| 楢の実 | みのらなば くいてすていく はならのみ 実らなば喰いて捨ていく葉楢の実 |
通称どんぐりとも言う 代表的などんぐりは椎・櫟の実 |
| 秋刀魚 | かくつんで まんさいさんま てんつくか 斯く積んで満載秋刀魚天突くか |
字が示すように秋に北から南下してくる刀の形をした魚 三陸の 海では十月下旬頃から最盛期を迎える |
| 糸 瓜 | てでへちま たしかめかした まちへでて 手で糸瓜確かめ課した街へ出て |
熱帯アジア原産の観賞用植物の果実で実丈は30〜60cmにも なる へちま水は咳止めの薬や化粧水にも使われる |
| 木の実 | まだのんき このみかみのこきんのたま 未だ呑気木の実神の子金の玉 |
椎・楢・橡・櫟・栗・椿の実・・etsなどを総称して木の実と 称ぶ 食べられるものと食べられないものとがある |
| 蝗 | たで まつま いなごは こない まつまでだ 田で待つ間イナゴは来ない待つまでだ |
直翅目の昆虫で体長3cmくらい 稲の害虫でもある 以前は佃煮として食されたが最近は余り見かけなくなった |
| 錦 木 | にしきぎは はがちりちかは はききしに 錦木は葉が散り地下は掃ききしに |
花は黄白色 実は真紅 紅葉が美しい |
| 冬 瓜 | かんきにて とうがんかうと てにきんか 還気にて冬瓜買うと手に金貨 |
インド原産のウリ科のつる性一年草 雄雌同株 果実は円形から楕円形 あんかけや冬瓜汁として食す |
| 行く秋 | かんせんをゆくあきあくゆおんせんか 幹線を行く秋飽く湯温泉か |
秋の終わりを言う 他に秋の名残・秋の別れ・秋の限り・帰る秋 などが同義語として使われている |
| 身に入む | とまりなどむしにみにしむとなりまど 泊りなど無視に身に入む隣窓 |
心の底まで染みわたる の意だが季節的には無関係のようにも 思える 秋はそれだけ感傷的になりやすいからなのかも知れない |
| 季 語 | 【冬 季】 | 季語の説明 |
| 初 雪 | ふくがわにはつゆきゆづはにわかくふ 吹く側に初雪柚子葉俄か喰ふ |
その年の始めて積雪した雪 北海道の大雪山は十月にも冠雪する。 その日を予想し当てるイベントも毎年行われている |
| 年忘れ | すえおくも としわすれ すわじと もくをえず 据え置くも年忘れ吸わじとモクを得ず |
年末にその年を顧みて無病息災を祈念し宴を催す (同義語)・・忘年会 |
| 焚 火 | このなんを たきびよびきた おんなのこ 此の難を焚火呼び来た女の子 |
寒い日 戸外で暖をとるために焚く火のこと |
| ねんねこ | ねんねこと りもこん こもり とこねんね ねんねことリモコン子守床ねんね |
おんぶする子供を寒さから守るために覆う綿入りの防寒具 |
| 竹 馬 | こいながき たけうまうけた きかないこ 請い長き竹馬受けたきかない子 |
二本の竹の棒に足を載せせるように細工された子供の遊び道具 何故冬の季語なのか疑問が残るが冬に多く使われたからなのだろう |
| 雑 炊 | えぞおもい ぞうすいすうぞ いもをそえ 蝦夷思い雑炊吸うぞ芋を添え |
おじや とも言い味噌汁やちり鍋などの残ったものにご飯を 入れた保温食 確かに熱い雑炊は冬の御馳走だ |
| たま風 | しらぬもな たまかぜが また なもぬらし 知らぬも名たま風が又汝も濡らし |
季節風の吹き出しの呼び名 福井県の若狭湾以東の日本海沿岸で 呼び名が流布した 余り長く続かない突風のようなもの |
| 師 走 | かこみのち すわしてしわす ちのみごか 囲みのち吸わして師走乳飲み子か |
十二月の異称 忙しない年末は普段動かない師も走る程忙しい 所からこの呼び名になったらしい |
| 冬の日 | ふゆのひが しやも ひもやし かひのゆふ 冬の日が視野も火燃やし歌碑の夕 |
冬の日射し 又は冬の一日(ひとひ) |
| 雪しまき | ゆき しまき こきよの よきこ きまじきゆ 雪しまき濃き夜の良き娘来まじ消ゆ |
雪を伴った激しい風 |
| 氷 柱 | なむよりは もてり つららつりても はりよむな 南無よりは持てり氷柱吊りても梁読むな |
気温が零下4度を超すと軒先や崖から落ちる水滴が凍り棒状の 氷が連なる様を言う |
| 冬 至 | ほしのみか とうじにじうと かみのしぼ 星のみか冬至に慈雨と神の思慕 |
陰暦十一月の節で立冬より四十五日後 陽暦では十二月二十二日 から二十三日頃に当たる 夜が一番長い日 (対象語 夏至) |
| 短 日 | ふのしぬいたんじつしんだいぬしのぶ 布延し縫い短日死んだ犬偲ぶ |
夜が長いという事即ち日が短い事だから短日として冬の季語と したのは納得するがならば(秋の)夜長は理屈に合わない気もする |
| 風 花 | すながうつかざはなはさかつうかなす 砂が打つ風花は坂通過なす |
晴天にちらつく雪の事を言い風下の山麓地方に多い |
| 霙 | つまるはなみぞれなれそみなばるまつ 詰まる鼻霙慣れ染み名張る松 |
冬 地表の温度が上がってくると降る雪が中空で解け雨混じりの雪 が落ちてくる 初雪の頃や冬の終わり頃にこの現象が起こる |
| 凍れる | しばるるはみずはればすみはるるはし 凍るるは水張れば澄み晴るる橋 |
空気が乾燥し晴れた真冬の朝身を切るような寒さを感じる。 (しばれる)は方言から発祥した季語 |